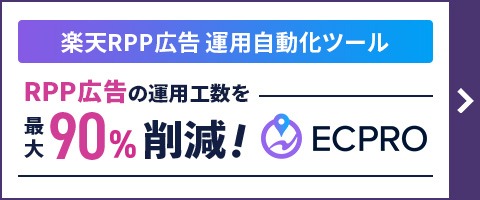Amazonスポンサープロダクト広告運用を最適化する4つのコツ
amazon
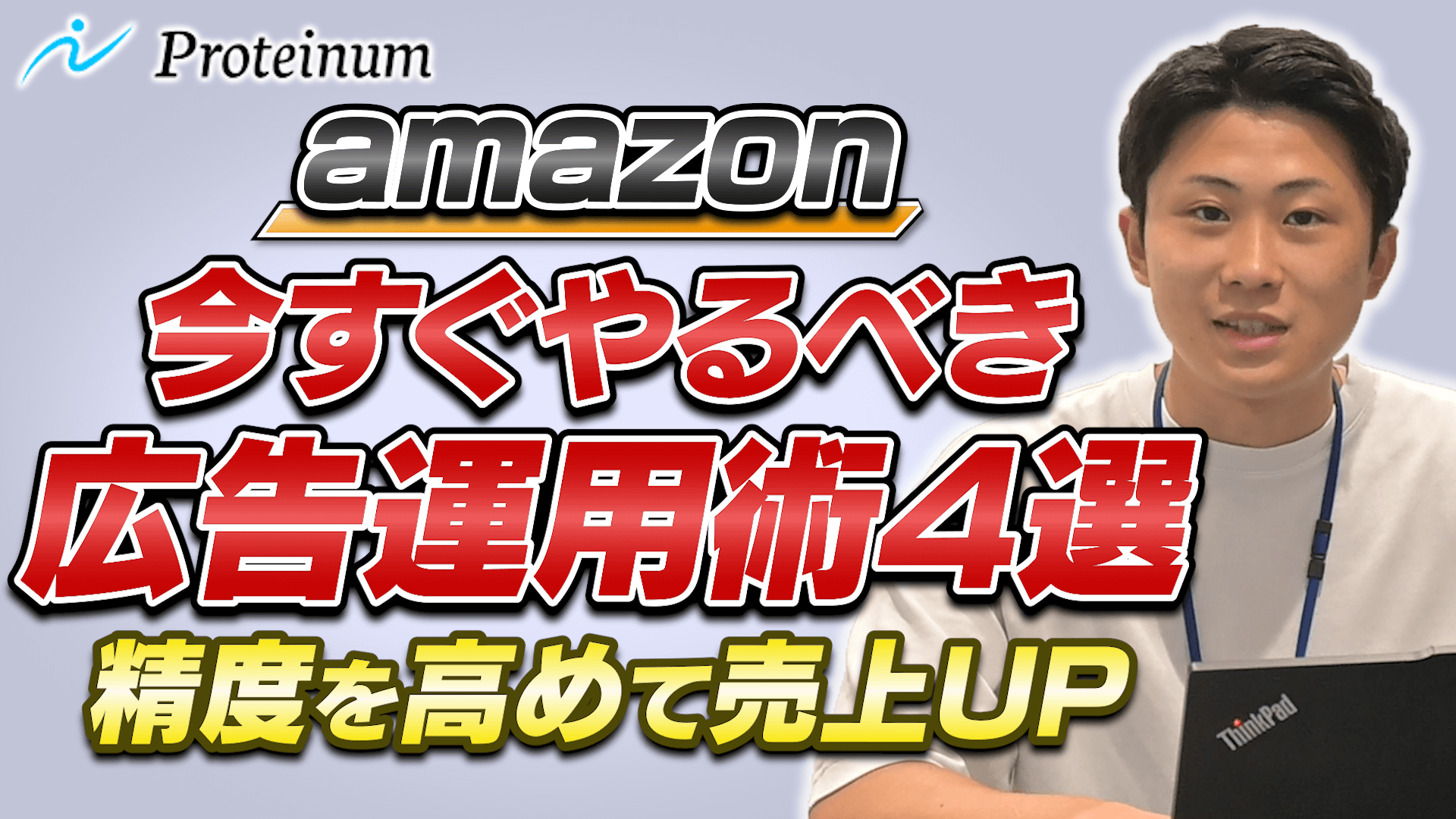
こんにちは、プロテーナムのコンサルタント伊東です。本日は、Amazonスポンサープロダクト広告運用のコツについて、皆さんが「思ったよりも広告効果が出ない」「もっと効率を上げて配信したい」と感じている状況を改善するための具体的な4つのポイントをお伝えします。この内容を実践することで、広告のパフォーマンスを大幅に向上させることができるでしょう。
Contents
1. スポンサープロダクト広告のキャンペーンの適切な構成
Amazon広告を効率的に運用するためには、大きく3つのタイプのキャンペーンを意識して構成することが重要です。
- オートターゲティング広告
- 仕組み: Amazonが自動的にキーワードや商品を特定し、広告を配信してくれる機能です。
- 活用目的: 新しい検索キーワードを発見するための「検索用広告」として活用します。
- 最適な状況: 特に広告出稿初期の段階や、商品にまだ十分な実績がない場合に非常に有効です。
- マニュアルターゲティング広告(指名キーワード設定)
- 仕組み: ブランド名や商品名など、すでに購入意欲が高いユーザーが検索するキーワードに狙いを定めて出稿する方法がおすすめです。
- 例: 「プロテイン × ブランド名」や「サプリメント + ブランド名」といった形で、指名検索された際に確実にアプローチします。
- 特徴: コンバージョン率や費用対効果(ROAS)が非常に高く出やすい傾向にあります。
- マニュアルターゲティング広告(非指名キーワード設定)
- 仕組み: 「一眼レフカメラ」や「プロテイン 女性向け」のように、まだ具体的な商品は決まっていないものの、探している商品の種類が決まっているユーザー向けの広告設定です。
- 特徴: 購入につながるポテンシャルはありますが、どのキーワードから実際に購入まで獲得できるかは配信してみないと分かりません。
- 運用ポイント: 配信設定後、無駄なクリックを防ぐために分析と調整を徹底することが重要です。
これら3つの構成を意識してキャンペーンを作成することで、新規キーワードの発掘から、成約率の高いキーワードへの集中まで、幅広く広告運用を最適化することが可能になります。
2. スポンサープロダクト広告のレポートで配信の偏りの確認
広告の成果を最大化するためには、配信の偏りがないか定期的に確認することが不可欠です。広告レポートで確認すべき主な項目は以下の2つです。
- 広告タブ
- 確認内容: 商品別の成果を確認し、効果の低い商品に広告配信が偏っていないかをチェックします。
- 対応策: もし著しく効果の低い商品があれば、配信を停止するか、キャンペーンを分けて適切な配信設定に調整します。
- ターゲットタブ
- 確認内容: 特定のキーワードやASINへの配信に偏りすぎていないかを確認します。広告費を消費順に並び替えることで、消費が多いターゲティングから順に確認できます。
- 対応策: 配信が偏っている場合は、入札額を調整するか、一時停止して他のターゲットでも配信できるように対応します。
- 高パフォーマンスのターゲット: もし特定のターゲットの効果が非常に高い場合は、そのターゲット専用のキャンペーンを作成し、さらに強化することも有効な選択肢です。
- 配信が偏っている場合のリスク: 例えば、オート配信キャンペーンで自社ブランド名や商品名ばかりに配信が偏っている場合、新規ユーザーに広告が届いておらず、広告がなくても購入していたであろうユーザーに配信している可能性があります。このような場合は、検索レポートで実際に売上につながったキーワードを確認してください。
3. スポンサープロダクト広告の入札額(CPC)の方針別の調整
入札額の調整は、広告運用の目的によって方針が変わります。
- 利益重視・ROAS改善を優先する場合
- 調整方針: 目標ROASに対し、ROASの低いターゲティングのCPC(クリック単価)を下げます。
- ポイント: スポンサープロダクト広告では、推奨入札額未満でも広告が表示される場合があります。目標ROASから逆算し、推奨入札額に縛られずCPCを下げて構いません。
- 注意点: CPCを下げて配信がされなくなった場合は、該当ターゲティングのステータスを停止し、新しいターゲットを追加することを検討してください。また、CPCを下げる際には、該当キーワードのCVR(コンバージョン率)やインプレッション実績も確認しましょう。例えば、インプレッションは多いのにCVRが低いキーワードは、商品画像の改善などで配信効果を高められる可能性があります。
- 新規顧客獲得重視の場合: 指名キーワードは広告配信がなくても購入される可能性が高いため、新規獲得目的では不必要な可能性があります。ROAS重視で非指名キーワードのCPCを下げた結果、指名キーワードばかりに配信が偏らないよう注意が必要です。
- 売上アップ・トップラインの引き上げを優先する場合
- 調整方針: 売れているキーワードのCPCをしっかりと上げて、表示機会を最大化します。
- 考え方: すでに高いROASを出しているターゲティングにより多くの広告を配信することで、キャンペーン全体の売上増加につながります。
- 注意点: 入札単価を上げると広告費が増加するため、ROASが一定以上維持されていることが前提となります。ターゲットごとのROASの加減値を意識し、その加減値を下回らないように入札額を上げることが重要です。
4. 検索レポートの徹底活用
検索レポートは、ユーザーが実際に検索したキーワードと、それに対する広告の成果を確認できる非常に重要なツールです。
- 売上に貢献したキーワードの特定
- 活用方法: 例えば「プロテイン 無添加 女性向け」といったキーワードで商品が売れていた場合、そのキーワードは価値があると判断できます。
- 対応策: これらのキーワードをマニュアルターゲティング広告に追加し、さらに細かく調整していくことで、効果を最大化します。
- クリックされても購入につながっていないキーワードの特定
- 活用方法: 例えば「プロテイン 送料無料 激安」といったキーワードが50件以上クリックされたにもかかわらず、購入が0件だった場合、費用だけが無駄にかかっている状況です。
- 対応策: このようなキーワードは除外キーワードに設定しましょう。ネガティブターゲティング機能から簡単に設定できます。
- 定期的な確認の習慣化
- 推奨頻度: まずは週1回を目安に、クリック数と注文件数でフィルターをかけて確認することをおすすめします。これにより、改善点が見つけやすくなります。
- 効果: この作業を習慣化することで、広告費の無駄を削減し、より効果の高いところに配信を強化できるため、キャンペーン全体のパフォーマンス向上に大きく貢献します。

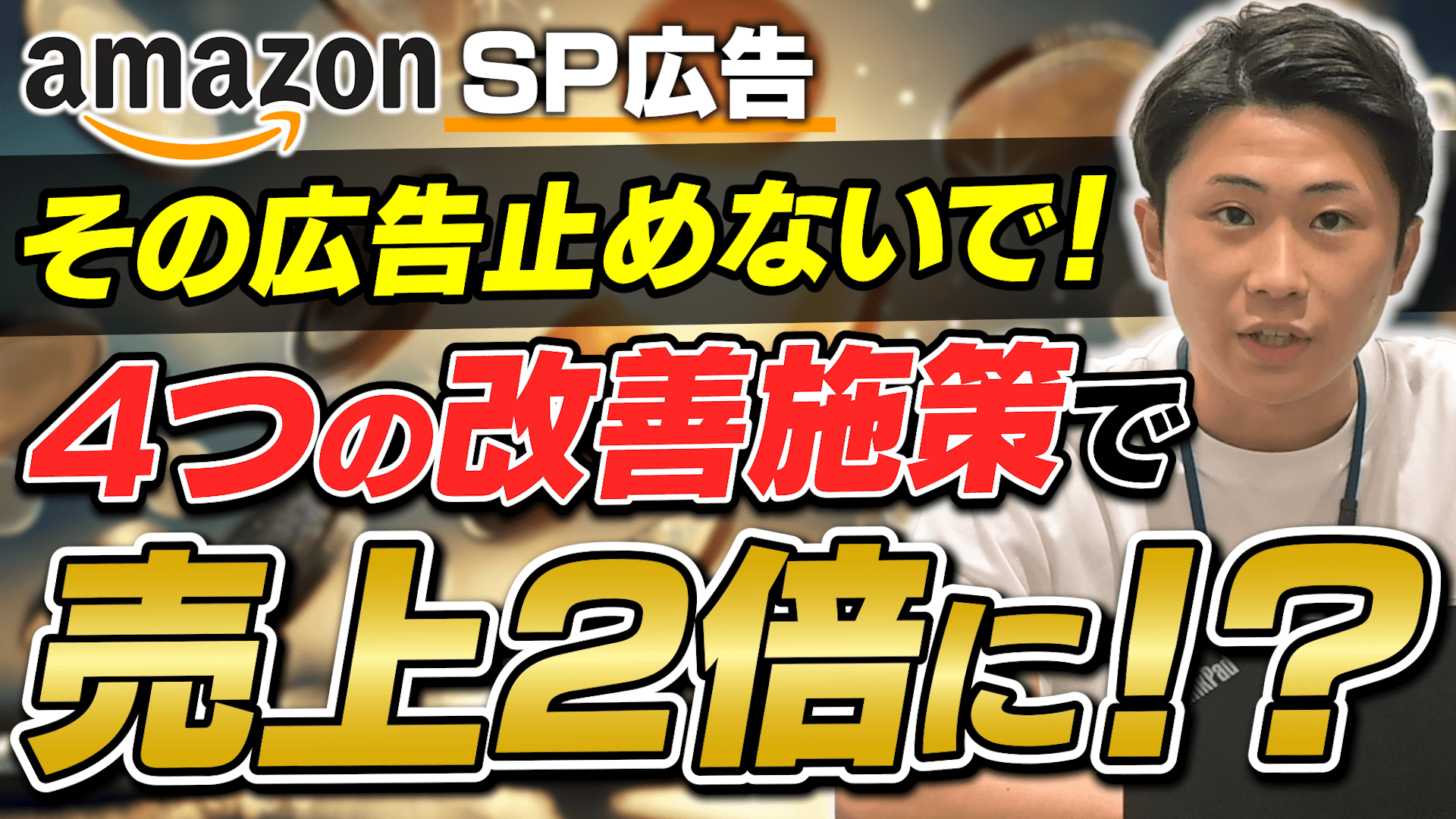 【Amazon】スポンサープロダクト広告の売上が2倍に?Amazon運用で不可欠なCVR改善ガイド
【Amazon】スポンサープロダクト広告の売上が2倍に?Amazon運用で不可欠なCVR改善ガイド 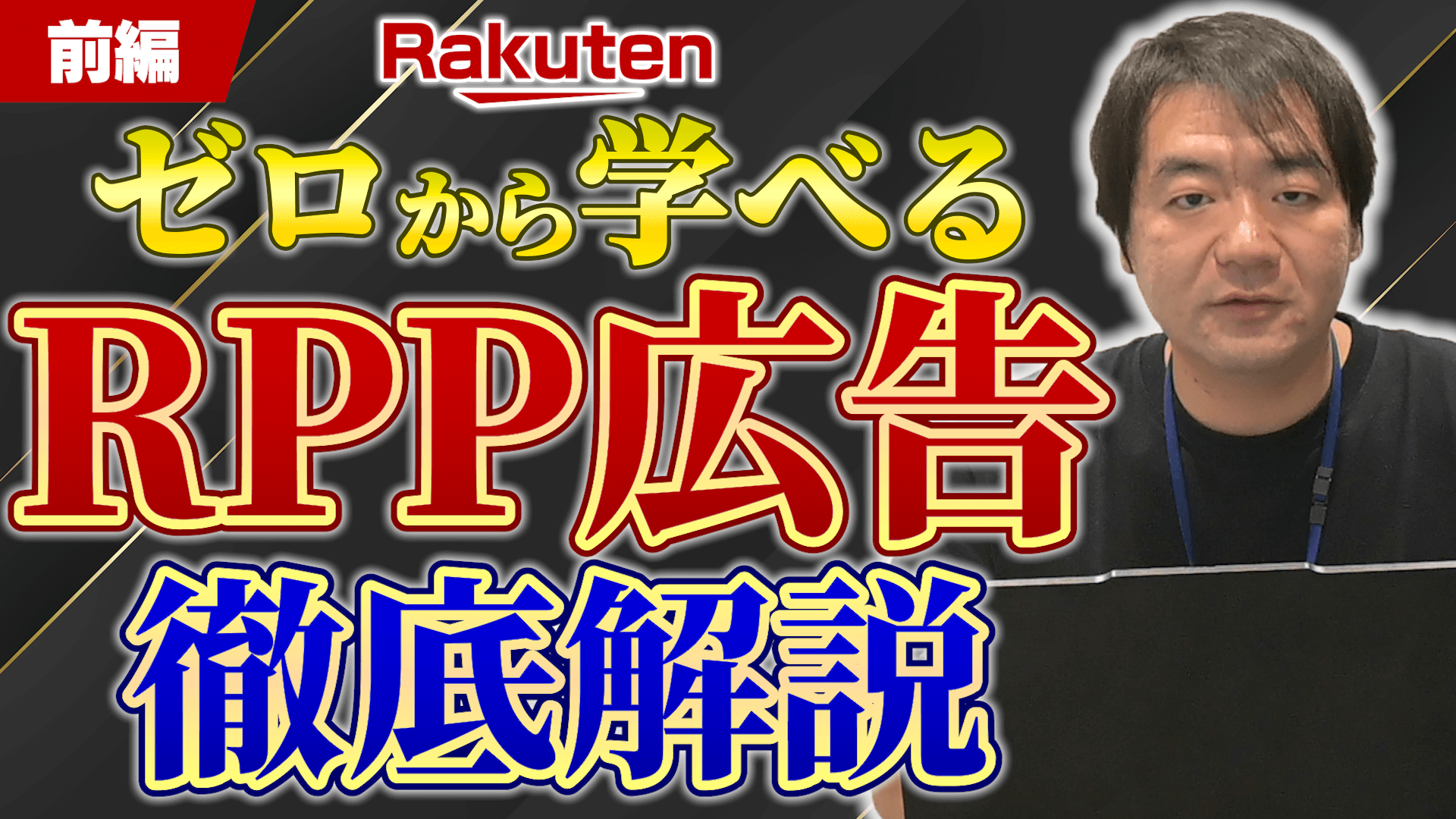 【楽天市場】RPP広告解説完全版 | 考え方から細かい運用例まで(前編)
【楽天市場】RPP広告解説完全版 | 考え方から細かい運用例まで(前編) 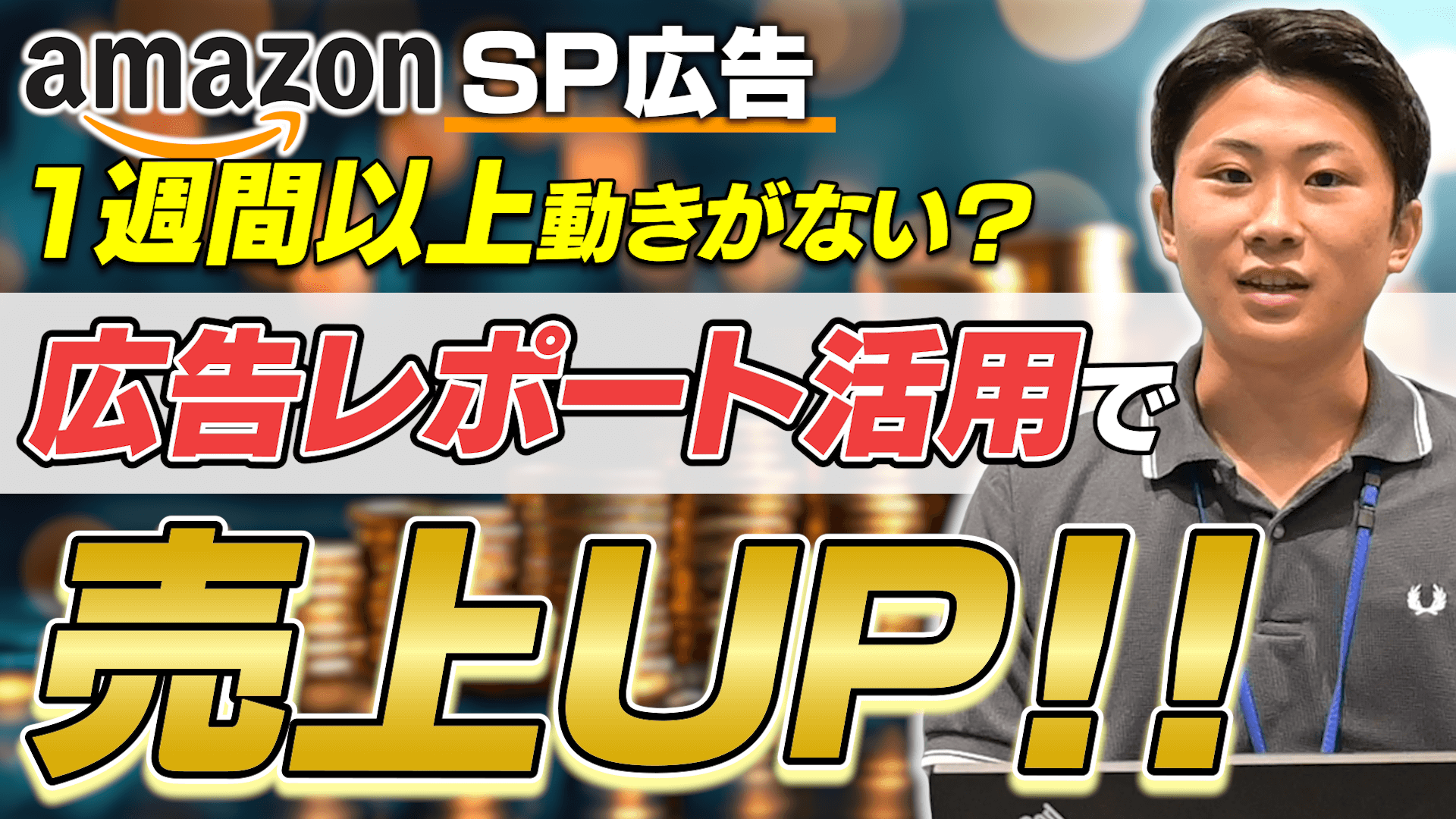 【Amazon】Amazonスポンサープロダクト広告のレポート活用で費用対効果を最大化!具体的な調整・改善手順を徹底解説!!
【Amazon】Amazonスポンサープロダクト広告のレポート活用で費用対効果を最大化!具体的な調整・改善手順を徹底解説!! 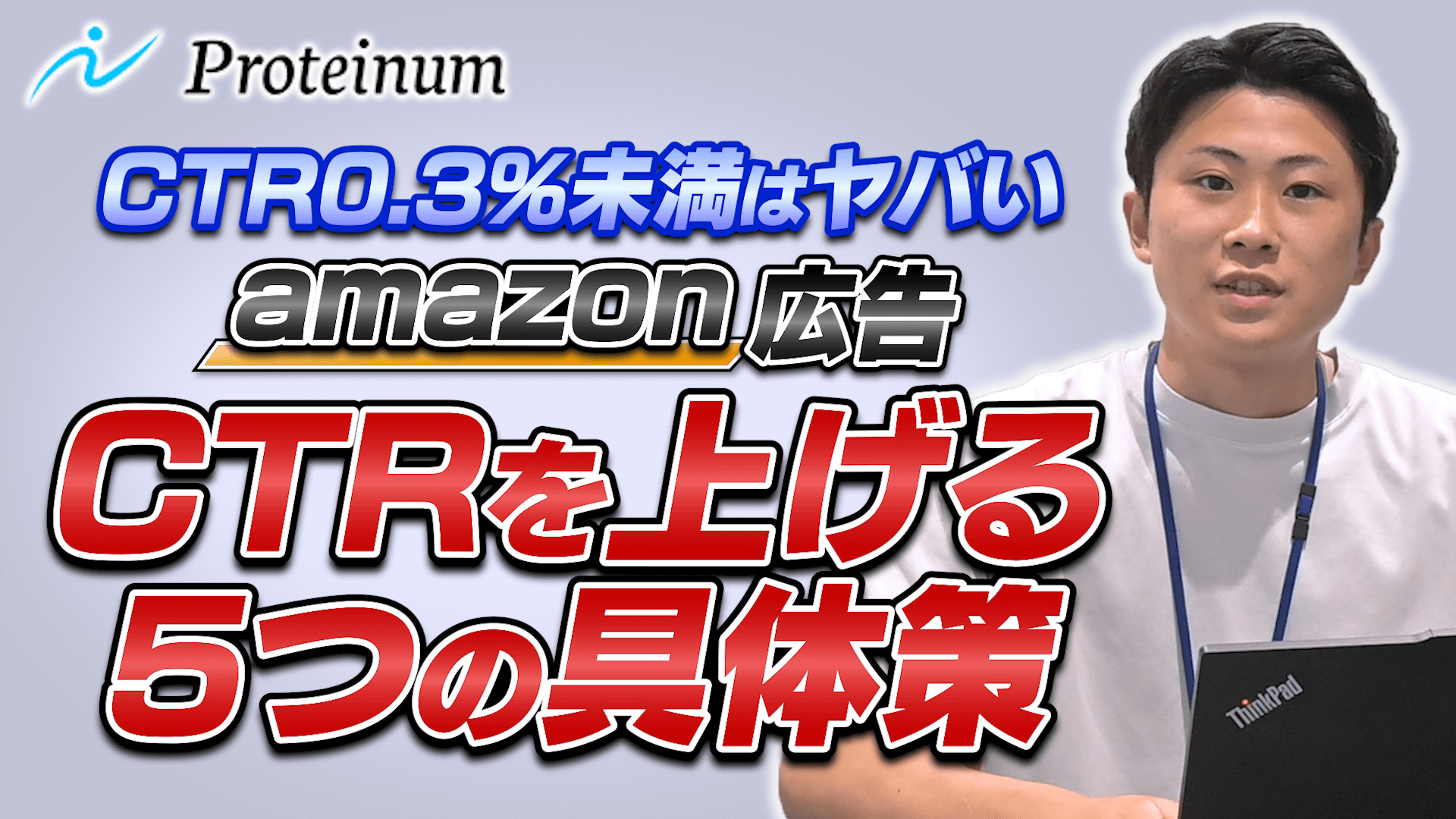 【Amazon】スポンサープロダクト広告のCTRを劇的に引き上げる5つの施策
【Amazon】スポンサープロダクト広告のCTRを劇的に引き上げる5つの施策